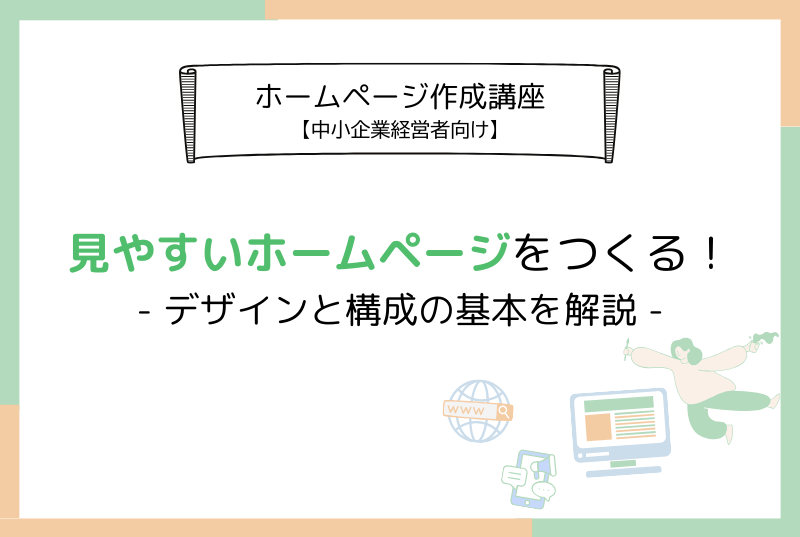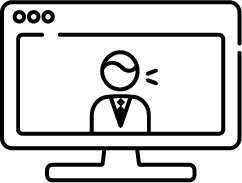みなさん、こんにちは。
経済産業省推進資格のITコーディネータ(認定番号0104242013C)の島田慶資です。
ホームページの「見やすさ」は、信頼性やビジネス成果に直結する重要な要素です。もし情報が探しにくく、どこに何があるか分からないホームページだった場合、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。
一方、直感的に操作できるホームページは、ユーザーがストレスなく情報にたどりつけるため、ブランド構築やコンバージョン増加につながります。そこで、「見やすさ」がなぜ重要なのかを解説したうえで、すぐに実践できる改善ポイントをお伝えします。
目次
「見やすさ」がホームページに重要な理由
ホームページの見やすさは、ユーザーの第一印象やサイト滞在時間、最終的なコンバージョンにまで大きな影響を与えます。情報を見つけやすく、ストレスなく使えるEWBサイトは、ユーザーに安心感を与え、行動を促すからです。そこで、「見やすさ」がなぜ重要なのか詳しく解説します。
情報を見つけやすいため
ホームページが見やすければ、ユーザーはそれだけ探している情報を簡単に見つけることができます。逆に、WEBサイトの構造が複雑だったり、どこに何があるか分かりにくければ、ユーザーが目的の情報にたどりつけず、ストレスを感じてしまいます。
ホームページにアクセスしたユーザーの多くは、素早く情報を見つけたいと考える傾向があるため、ストレスを感じさせることは企業のイメージダウンや離脱を招くことになります。
ブランド構築に役立つ
ブランド構築という点からも、ホームページの見やすさは重要です。なぜなら、WEBサイトの見た目は、ユーザーが会社に対して抱く最初の印象に大きく影響するからです。
例えば、きれいに情報が整理されていて、探しているものにすぐにたどりつけるデザイン・構造であれば、ユーザーはプロフェッショナルで信頼できる会社だと感じます。逆に、ごちゃごちゃしていて使いにくいWEBサイトだと、「この会社は大丈夫かな」と不安を感じさせ、ユーザーが情報を探すことを諦めてしまいます。このように、見やすいホームページは会社のブランド構築に役立ちます。
コンバージョンに影響するため
情報が整理されていて、ナビゲーションも分かりやすいホームページは、ユーザーが迷うことなくスムーズに情報を探すことができるため、コンバージョンにつながります。一般的に、見やすいホームページの方が、ユーザーはWEBサイトに長く留まりやすく、問い合わせや購入といった次の行動を起こしやすいです。収益向上を目指すのであれば、ホームページの見やすさは必須の要素です。
見やすいホームページをつくるポイント
どれだけ魅力的な情報を載せても、ホームページが見づらければユーザーにメッセージが届きません。ナビゲーションやデザイン、文字の見せ方など、見やすいホームページを作るために工夫できる点は複数あります。そこで、ユーザーにとって「見やすい」と感じてもらうためのポイントを解説します。
関連記事:ホームページの作り方を解説!ツールごとの比較などお伝えします
分かりやすいナビゲーション
ホームページを見やすくする大切なポイントの1つは、分かりやすいナビゲーションです。Webサイトを訪れたユーザーが道に迷わず目的の情報にたどり着けるように、ナビゲーションにはページ間の移動をスムーズにする役割があります。
もしナビゲーションが複雑だと、どこにいけば何があるか分かりにくく、ユーザーはWEBサイト内で迷子になり、離脱を招きます。そのため、ナビゲーションはシンプルで、分かりやすい場所に配置してください。
明確なCTA
CTA(コール・トゥ・アクション)も見やすいホームページを作るのに重要な要素です。CTAとは、ホームページを訪れたユーザーに何をしてほしいのかを示すボタンやリンクのことです。例えば「詳しくはこちら」「資料をダウンロード」「お問い合わせ」などが一般的なCTAです。明確なCTAは、ユーザーを迷わせることなく次の行動へスムーズに誘導できるため、コンバージョン率を高めるためにも大切です。
読みやすいタイポグラフィ
読みやすいタイポグラフィも重要なポイントの1つです。タイポグラフィとは、ホームページで使われる文字のフォントの種類、サイズ、行間や文字間のスペース、そして一行の長さといった、文字の見せ方全般のことです。この文字の見た目が整っていないと、ユーザーはテキストを重苦しく感じたり、読むのに疲労してしまい、せっかくのメッセージが伝わりにくくなります。
例えば、読みにくいフォントを使ったり、文字が小さすぎたり、行間が狭く文字がぎっしり詰まっているなどのことは、よくあるタイポグラフィの問題です。逆に理想的なのは、ホームページの目的に合ったシンプルなフォントを使い、文字のサイズや行間、一行の長さを読みやすいように適度に調整されているものです。読みやすいタイポグラフィは、単に見た目を良くするためだけでなく、ユーザーがホームページを快適に利用し、コンバージョンにつなげる基礎となります。
ホワイトスペース
見やすいホームページを作るうえで重要なのがホワイトスペースです。ホワイトスペースとは、文字や画像の周囲にある空白部分のことで、情報を詰め込みすぎず、適度な余白を取ることで、コンテンツが読みやすくなり、視線の流れも自然に整います。
ごちゃごちゃした印象を避け、使いやすいWEBサイトだと感じてもらうためにも、デザインの中に余白を意識的に取り入れるようにしてください。
使用するカラーを絞る
あまりにも多くのカラーを使い過ぎると、ユーザーの目に与える負担が大きくなり、見にくいホームページになってしまいます。そのため、ある程度使用するカラーを絞るようにしてください。理想をいえば、1つのページで使用するカラーを3~4色程度にすると視認性が向上します。
一貫性のあるデザイン
ホームページは全体として、一貫性のあるデザインにする必要があります。例えば、ページごとに使われる色やフォントが変わったり、ナビゲーションの場所や項目名が変わると、ユーザーが「これは別のWEBサイトなのか」と勘違いしたり、探している情報がどこにあるか分からなくなってしまいます。
ホームページにある各要素が整っていることは大切ですが、最終的にはWEBサイト全体で一貫していなければいけません。色使い、タイポグラフィ、画像といった各要素の一貫性を保つことで、ブランドのイメージが強まり、ユーザーはそのWEBサイトが同じ会社のものであると認識しやすくなります。
表示速度の最適化
表示速度の最適化も、見やすいホームページにするために重要です。表示速度とは、ユーザーがホームページを閲覧した際に、パソコンやスマートフォンの画面にページが表示されるまでの速さのことです。
もしWEBサイトの表示に時間がかかりすぎると、ユーザーは待っている間にストレスを感じ、諦めて他のWEBサイトに移動してしまう可能性が高まります。特にモバイル端末でWEBサイトを見る人が増えているため、表示速度の速さはますます重要です。
理想的には、ホームページは2秒以内に表示されるのが望ましいとされており、3秒を超えると離脱する人が増えていきます。表示速度改善のためには、画像を軽くしたり、不要な機能を減らすなどの工夫をして改善します。
慣習に従う
見やすいホームページを作るには、慣習に従うようにしてください。多くの人がインターネットでホームページを閲覧する際に「この情報はページのここに置いてあるだろう」「このボタンを押せばこうなるだろう」と無意識のうちに理解している共通のルールや配置があるので、自社のホームページでも、それに合わせることです。
例えば、多くのWEBサイトでナビゲーション(メニュー)はページの最上部や左側にあり、会社情報やプライバシーポリシーといった情報はページの最下部(フッター)に置かれています。こうした慣習に従うことで、訪問者は新しく訪れたWEBサイトであっても、どのように操作すれば良いかをすぐに理解でき、迷うことなく目的の情報にたどり着くことができます。これを大きく変えてしまうと、逆に使いにくいWEBサイトになってしまうため注意してください。
関連記事:WordPressでホームページを作る方法!手順や費用など解説
見やすいホームページをつくる手順
ホームページの見やすさは、ユーザーの滞在時間や問い合わせ数に大きく影響します。どんなに良い商品やサービスを紹介していても、情報がごちゃごちゃしていては伝わりません。そこで、初心者でも実践できる「見やすいホームページをつくる基本手順」を分かりやすく解説します。
ターゲットを明確化
最初のステップは、ターゲットを明確化することです。誰にホームページを見てもらいたいのかをはっきりさせることで、これ以降の作業も、適切に進めることができるからです。ターゲットとするユーザーが何を求めているのか、どんな情報が必要なのかを整理し、その人たちに「分かりやすい」「使いやすい」ページを作ってください。
どんな内容(コンテンツ)を載せるか、どのようなデザインにするか、そして情報がどこに配置されていれば見つけやすいかといったことは、ターゲットが明確になることで決めやすくなります。そのため、ターゲットの設定を一番最初におこなってください。
伝えたいことを決める
ターゲットが明確になれば、次はホームページにどんな内容(コンテンツ)を載せるべきか、どのようなデザインが良いかなど、伝えるべきことを明確にします。ユーザーはホームページに来てから5秒以内に「ここはどんなサイトで、何ができて、なぜ自分にとって価値があるのか」を判断します。そのため、ターゲットに合わせた、分かりやすいメッセージをできる限り早い時点で伝えるようにしてください。
サイト構造を検討
見やすいホームページを作るための次のステップは、サイト構造を検討することです。これはホームページ全体の設計図を決める作業で、具体的にはどんなページが必要か、それぞれのページがどのようにリンクしているかなどを検討します。ユーザーがWEBサイトの使い方を直感的に理解でき、知りたい情報を効率的に見つけられるようにするのが目標です。
デザインする
次にデザインをします。これは、ホームページの見た目や使い勝手を具体的に形にし、先ほど決めたサイト構造に沿って、ユーザーが伝えたい情報に迷わずたどり着けることを目指します。デザインには、サイトの色合い、文字の種類や大きさ(フォント)、写真やイラストなどの画像、そしてページ上の要素の配置(レイアウトや余白) といったものが含まれます。これらの要素を、シンプルで分かりやすく、かつ統一感があるように整えることが重要です。
また、多くの人がスマートフォンでホームページを閲覧するため、どんな画面サイズでも見やすく、操作しやすいデザインにすることも忘れないようにしてください。
公開前のチェック
デザインが完了したら、すぐにホームページを公開したくなりますが、その前に第三者のチェックをするようにしてください。できれば、自社のことをまったく知らない人にホームページをみてもらい、操作に迷っていないか、メッセージ内容が正しく伝わっているかということを確認します。具体的には、次のように尋ねます。
- 自分が目的とする情報を迷わず確認できたか?
- トップページでメッセージを理解できたか?
- 製品情報を正しく把握できたか?
このように第三者にホームページを確認してもらったら、フィードバックをもらい、必要に応じて修正をします。この事前のチェックをおこなうだけでも、見やすいホームページをつくるのに大いに役立ちます。
ホームページの公開と改善
デザインを施したあとは、いよいよホームページを公開します。ホームページの公開は、これまで取り組んできたことの集大成であると同時に、WEBサイトの目的達成に向けたスタート地点でもあります。
ここから実際の運用を通じて、本当に伝わるホームページに育てていくフェーズに入ります。具体的には、ホームページを訪れたユーザーがどのように操作しているかを観察し、そこから見えてくる改善点を見つけ、WEBサイトを良くしていくための施策をとります。
どれだけ計画やデザインに時間をかけても、実際にユーザーが自社ホームページを使ったときに「分かりにくい」と感じる部分や、目的の情報にたどり着けずに離脱してしまうケースが必ず出てきます。そのため、GA4やマイクロソフトClarityのようなツールを使い、ユーザーがWEBサイトのどこで離脱しているのかを確認し、1つひとつ改善してください。
まとめ
ホームページの「見やすさ」は、ユーザーの体験を大きく左右し、情報の伝達力やブランドの信頼性に直結します。ナビゲーションやデザインの一貫性、読みやすい文字の設定など、細かなポイントを丁寧に調整していくことで、ユーザーにとって快適で分かりやすいWEBサイトが実現できます。また、公開後もユーザーの行動を観察しながら改善を重ねていくことが、より良いサイト作りの鍵となります。今回の内容を参考に、ぜひ見やすいWEBサイトの構築を実現してください。